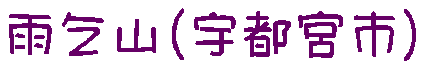
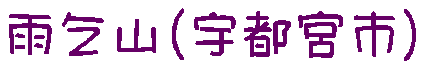
標高 約360m
|
ジョージ・レイ・マロリーの有名なセリフを借りなくとも、人が山に登る理由はいろいろと答えることができるだろう。
たとえば栃木県人のけむぞういわく、「ここに海がないから」だと。
まあ海に行く代わりに山に行くわけじゃあないけどね。
今回のこの雨乞山だが、新里町のこの地区に低い山があるのは以前から知っていたものの特に登ってみようとは考えていなかった。近くに他の山もあるしね。
しかし、地形図をよく見るとなかなか複雑で面白そうな地形じゃあないかい?
さらに情報を集めると山行記録も見つかった。
こうなったら行くしかねえぜ。
名前の通り雨乞い伝説が伝わるこの山は、三つの峰が東西にならんでいる。ここを西から東へ向かって縦走するルートだ。東峰に333mの標高点があるが、最高点は中央峰の標高約360mになる。
|
![]()
 |
舗装林道の行き止まり地点から右手に見える斜面を登る(頁下写真、上左)。登りきった所から有刺鉄線の柵沿いに左手に進みピークに立つ。
が、西峰にしては低い。よくよく位置を確認すると西峰南尾根端の小ピークだった。位置を確認している時コンパスが狂ったのかと思ったぞ。
気を取り直して西峰へと落ち葉に足を取られながら息を切らして登る(左写真)。
西峰のピークで水を飲もうとザックを下ろすと財布とケータイの入ったポケットのファスナーが全開だった。あぶねええええ
|
![]()
西峰〜中央峰の鞍部からの登りは、斜面に落ち葉も積もらないくらいの急登だ(右写真)。立ち木につかまりながらやっとの思いで登頂(頁下写真、上中)。木々の間から鞍掛山や半蔵山周辺の山々が近くに見える。
何もない中央峰山頂を後にする。が、下りもキツい。体を横にしてズリ落ちる感じで下るも、高さ2mくらいの岩の上で行き詰る。ここを落ち葉まみれになって慎重に降りる。このルート中で二番目にスリリングだった。
一番はザックのファスナー全開。
降りてからよく見ると南側に巻き道があるじゃん。
|
 |
![]()
 |
東峰に入ると踏み跡がはっきりしてくる上に、赤いビニール紐の目印でルートを追っていける。
途中、幅の広い作業道の分岐があるがここは尾根をキープ(頁下写真、上右)。明るくていい道だ(頁下写真、下左)。しばらく進むと、この山随一の眺望ポイントに着く(左写真)。中ヒャッホーくらいの良い眺めだぜ。
東峰からの下りは広いフカフカした土の斜面をまっすぐ降りていく(頁下写真、下中)。山裾の墓地の横へ降りて、雨乞山探検は無事終了だ(頁下写真、下右)。
さて今回、木に付いた赤いものを追っていくという子供の頃の柿ドロボーの技が生きたわけだが、当時名人といわれたスカートめくりの技はどこかで生かせないもんかね。
|
![]()
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ● トップページ | ● このサイトについて | ● 羽黒山(鶴田町) | ● 上欠町 138,2mピーク | ● 戸室山 | ● 磯山(真岡市) | ● 仏生寺 芳賀新四国八十八か所霊場 | ● 浅間山(二宮町) | ● |
| ● 釜川遡行(前編) | ● 釜川遡行(後編) | ● 坊主山 | ● 瓦谷町 205.1mピーク | ● きのこ山 | ● 千渡山 | ● 多気山 南面 | ● 盗人岩(日光市) | ● |
| ● 猪倉城跡 | ● 鞍掛山 西峰 | ● 高所(那須烏山市) | ● 雨乞山(宇都宮市) | ● 岩崎 444mピーク | ● 盗人岩 東尾根 | ● 城山尋常小學校南校 學道 | ● 岩本観音 三角点峰 | ● |
| ● そこナニナムナム写真館 | ● そこナニ河川合流部写真館 | ● リンク集 | ● |